2024年の離島での活動を振り返ると、新たな試みが始まった年でもありました。
24年に春に行った離島タレントさん(利用者さん)との座談会では、それぞれの地域でのニーズを伺い、共通する資源不足(車社会であること・モビリティの課題、自身に合った福祉サービス・医療や治療の不足、物価が高い等)も見えてきました。
もちろん課題のみならず、働き始めてよかったこと、ポジティブなこともうかがえ、今回は座談会で出てきた意見を振り返りながら、昨年実施したワーケーションに関しても触れていき、新しい年に向けて私たちに改めて期待されていることを考えていきたいと思います。

(壱岐でのワーケーションの一コマ)
離島在住のタレント(利用者)の過去と現在
2024年12月末時点での離島在住の現利用者は、24名。南は先島諸島から、北は佐渡まで、11の島に点在しています。南から、宮古島6名、石垣島4名、沖永良部島1名、奄美大島1名、種子島1名、五島(上五島1名、下五島2名)、対馬3名、壱岐2名、佐渡3名。
これまで通算で41名が利用しています。その中で一般企業へ就職した方は8名で、就職率は19%となります。
東京都による令和4年度就労移行等実態調査による就労継続A型の一般就労への移行率は4.9%ですから、地方で展開していながら東京の約4倍の就職率ということになります。これは、福祉サービスである就労支援事業と並行して、障害者雇用支援サービス「サテラボ(サテライトオフィス)」の運営を行っていることが強く影響しています。
就労継続支援A・B型に繋がることでも働くことを切り口にした社会参加の機会提供になっていますが、その後に一般就労へと繋がることで、更に収入が増えたり、スキルが向上したり、キャリアパスが描きやすい状態を実現しています。
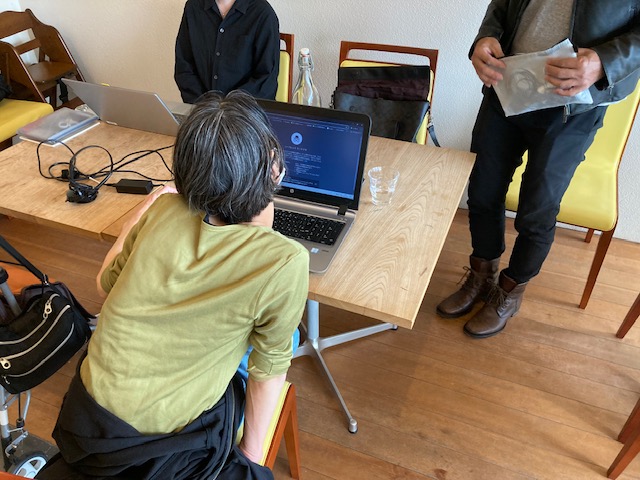
(作業の様子)
座談会から見えてきた課題の一例
座談会では、「ご自身の生活に当てはめて考えたときに『離島ならでは』だと感じる課題はありますか」という設問に対し、以下のような回答がありました。
– 就労関連:
– 完全在宅での就労以外が難しい
– ★就労先が少ない
– 離島における障害者向けの仕事の不足
– モビリティ:
– ★車社会である
– 1人での外出が難しい
– 移動が車がメインで環境を変えにくい
– 島外への移動が簡単ではない
– 島内にない施設の利用における交通の不便さ
– 物価とサポート体制:
– ★物価、特に燃料費が高い
– 外出や買い物などのサポート体制が整っていない
– 医療・福祉関連:
– ★医者の不足と訪問診察の不在
– 特定の科の受診日が限定的
– 離島での障害者福祉の支援と理解の遅れ
– 社会的な課題:
– 島外から来た人に対しての閉鎖的/排他的な反応
– 狭いコミュニティでの親戚や知り合いとの遭遇
– 通所と違い孤独を感じること
– その他:
– 電波のつながりの悪さ(沖縄はau系が優位、長崎はdocomo系が強い)
サンクスラボとして、直接的に解決できる課題としては福祉サービスの提供・雇用機会の提供(サテラボ)がありますが、モビリティや高い物価、医療資源の不足や「島ならではの文化」に関しては、なかなかすぐには課題解決は難しいなと感じています。このことは、離島に限らず過疎地域とも共通の課題であるはずです。
24年新たに始めた「ワーケーションプログラム」
座談会の中で、「離島の職員と同じ場で働く日を作ったら、来てみたいですか?」壱岐の職員である南の問いに対して、概ねその場にいた方がポジティブな意見をくださっため、「いつもの仕事場(家)と異なる環境で、一緒に仕事をしたり、昼食を食べたりしてみましょう」ということでスタートしたのがワーケーションプログラムです。
Vacation要素は皆無ですが、島内のおしゃれなカフェでリモートワークしようという試みで、今年度は壱岐と佐渡で試験的に実施しました。佐渡でのワーケーションの様子はこちらを拝読ください。
佐渡では、NPO法人探求Labo代表の尾崎さん(フレンチシェフ!)が場所や料理の提供をしてくれましました。尾崎さんが代表を務めるNPOでは、佐渡の若年者の起業家育成に力を入れており、地元高校内で「スタートアップ部」という起業を学ぶ部活を応援・支援しています。
自然豊かな佐渡の資源を活かして、島で若者が働き続けられるようにと尽力する尾崎さんが、今回のワーケーションのホストを引き受けてくれました。「障害や病気についてはあまりわからないことも多いけど、みんな同じ人間として、いろんな力があるはずだし、何かできることがあれば協力させてください」と快くおっしゃってくださり、今回のワーケーション実施となりました。
こうした地域との繋がりを作ることによって、様々なシナジーが生まれると思っています。例えば、多様性の推進。座談会で「島文化で狭いコミュニティなので障害が知られるとすぐに広まってしまう」といったことをおっしゃる方も複数おられました。
障害がコミュニティの中でネガティブなものとして捉えられ閉鎖的になっていくと、障害者自体の存在がおびやかされ、孤立していくことが容易に理解できます。そうならないためには、やはり実際に人と人が知り合っていくこと、繋がっていくことが、とても大切です。
社会的ステータスにとらわれずに、同じ島民として共生していくこと、社会的に弱い立場に置かれている人たちの社会的障壁が取り除かれていく世界では、誰もが生きやすい世界になることに違いはありません。
ワーケーションを通じて、地域を知ること、障害のある人に出会うこと、支援者と地域との繋がり、地産地消(地元で稼ぎ、地元で消費すること)が活発になれば、協力者も段々と増えていくはずです。2025年も、そんな繋がりを一つひとつ積み重ねていく取り組みを続けていきたいと思っています。

(佐渡のワーケーションでの一コマ)
2025年も、徹底的に現場の声を聴きながら
2024年はワーケーションの他にも、宮古島での利用説明会、石垣での障害者美術展の出展、壱岐でのPC教室などの取り組みも行ってきました。今年の各離島での取り組みも、当事者の皆さんの声を聴きながら、共同創造していけるように精進してまいります。ぜひ何らかの繋がりを作るための取り組みにご協力いただけるかたは、zaitaku@thankslab.bizまでご連絡ください。(記事:片山尚哉)



