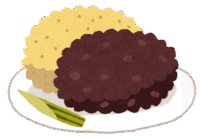こんにちは、久留米オフィスです😊
皆さんは、おはぎやぼた餅の呼び名が季節によって変わることをご存知ですか?
春:ぼた餅…牡丹の花にちなんで呼ばれます。
夏:夜船(よふね)…夜に作るお菓子で、「着き知らず(岸に船が着いても気づかないほど静か)」という昔の言葉遊びが由来です。
秋:おはぎ…萩の花にちなんで呼ばれます。
冬:北窓(きたまど)…北側の窓から月が見えないことから「月知らず」と呼ばれ、雪景色を眺めながら楽しむ和菓子として親しまれました。
つまり、どの季節でも中身は同じでも、名前や季節感を添えることで、より味わい深く感じられる工夫がされているのです✨
🌸 お彼岸におはぎやぼた餅を食べる理由
では、なぜお彼岸(春分・秋分)にはぼた餅やおはぎを食べるのでしょうか?
お彼岸は昼と夜の長さがほぼ同じになる時期で、仏教では極楽浄土が西にあるとされます。
この時期には、先祖や仏さまと近くでつながれると信じられてきました。
そのため、ご先祖さまに感謝するためにお墓参りをしたり、ぼた餅・おはぎをお供えしたりする習慣が生まれました。
また、小豆には古来より邪気を払う力があると信じられ、先祖へのお供え物としてぴったりとされました。
江戸時代になると砂糖が広く流通するようになり、甘いぼた餅やおはぎが一般の家庭でも楽しめるようになりました。
とはいえ、当時はまだ高価だったため、せめて先祖には良いものをお供えしたいという思いが込められていたのです。
🌟 A型事業所での「名前が変わっても本質は変わらない」
A型事業所での作業内容も、時期やプロジェクトによって変わることがあります。
しかし本質は変わりません。
「一般就労への移行を目標にする」
「社会参加・自立支援」
「働くための能力・スキルを身につける」
作業の内容や形が変わっても、“自分らしく働く力を育む”という本質は変わらないのです。
まるで季節によって名前が変わるおはぎのように、働き方や取り組みの形は変わっても、その中にある「成長」や「やりがい」、「社会とつながる喜び」はいつも同じ。利用者さんが安心して、そして楽しみながら取り組めることが、何より大切だと私たちは考えています。
これからも久留米オフィスでは、季節や個々のペースに合わせながら、働く喜びや成長を感じられる環境づくりを大切にしていきます😊
\ ご見学・ご相談、いつでもお気軽にどうぞ! /
久留米オフィスでは、見学・体験も随時受付中です。
「自分のペースで働きたい」「新しいことに挑戦してみたい」
そんな方もぜひお待ちしています😊
📞 久留米オフィス(0942-65-7278)